新生活のストレスと五月病
health
2025年4月18日
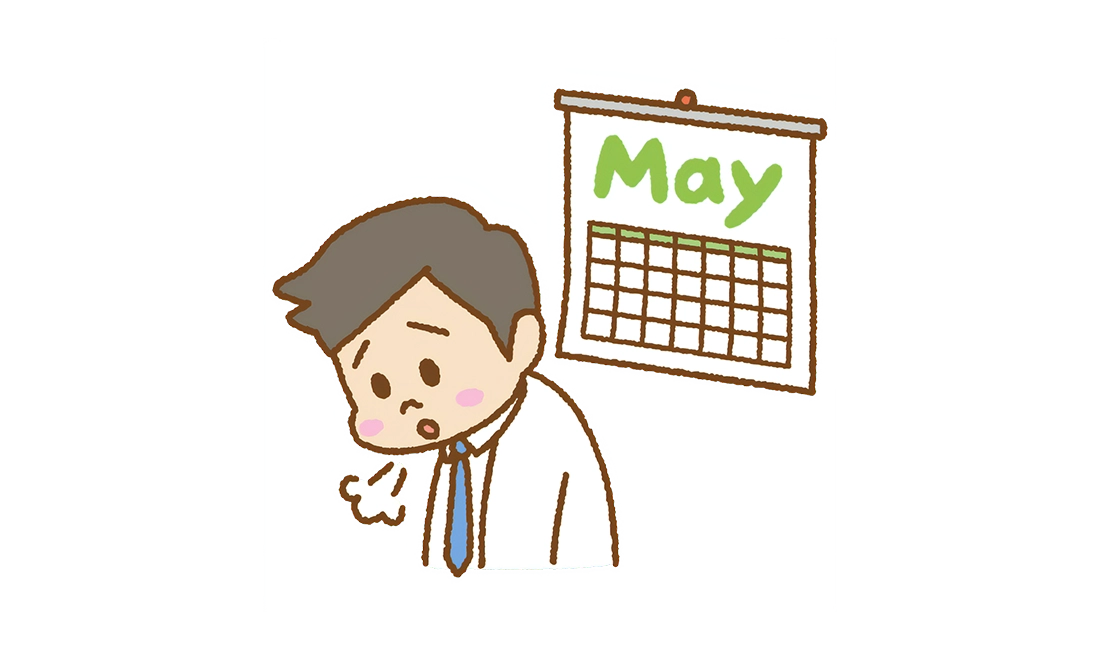
5月の連休明けに心身のバランスを崩してしまった状態を、日本では「五月病」と呼ぶことがあります。五月病を乗り越えるためには、心身の不調を理解し、適切な対策を講じることが大切です。
五月病とは
5月の連休明けに心身のバランスを崩してしまった状態を、日本では「五月病」と呼ぶことがあります。5月に不調を感じる方が多いことから、いわゆる総称として使われている言葉です。この時期は、いろいろと社会生活の変化、気候の変化などが重なる時期です。
そして日本ではゴールデンウイークがありますから、なおさら変化を大きく感じてしまうのかもしれません。もちろん医療機関で「五月病」と診断名が付くこともありません、診断名として使われるのは「適応障害」、もしくは「うつ病」とされることが多いです。
適応障害とは、新しい環境に適応できないことがストレスになり、心身に影響が現れ、生活に支障が出ている状態です。うつ病とは、脳の機能低下により心身に影響が出て、身体症状や精神症状が出ている状態です。ご自身で判断するのは難しいので、不調を感じた際は早めに医療機関に相談することをおすすめします。
五月病の原因
新社会人の始まりや、社内での役職変更など、4月は環境の変化が大きい時期です。
「新しい環境に溶け込まなければ!」と、気を張り続ける方もいるでしょう。
慣れない環境で過ごすうちに、心身の疲れを溜めてしまう人は少なくありません。
1. 環境や時間の使い方の変化
起床や就寝時間の変化、家を出る時間や帰宅時間の変化、人間関係の変化など、今までの生活との違いが大きいほど、慣れるまでには時間がかかるものです。
2. 人間関係の悩み
「苦手な人がいる」「今までの人間関係の居心地がよくて、新しい人たちとうまく付き合えない」など、初めて関わる人たちへの不安や不満はどうしても生まれがちです。
3. 目標の喪失
新しい環境で、これからがスタート!というところで、目標を喪失してしまう方もいます。
就職活動や転職活動ですべてを出し尽くして、入社後のモチベーションが残っていない。昇進を目指して努力していた結果、昇進後の目標を見失ってしまった。大きなプロジェクトを達成して、仕事のハリがなくなった。など、目指してきた目標をクリアしたことで、気持ちが燃え尽きてしまう場合があるのです。
4. 現実とのギャップ
自分が描いていた新生活と、現実の生活とのギャップも、ストレスの要因になります。
新生活がスタートした直後はどうにか日々をこなしていても、5月の連休中に自分の生活を省みて「こんなはずでは……」と落ち込んでしまう方もいるかもしれません。
五月病の症状
- • 気分が落ち込む
- • 仕事や勉強への意欲がなくなる
- • 集中力がなくなる
- • 疲れやすくなる
- • 寝つきや寝起きが悪くなる
- • 食欲がない
- • 動悸がする
- • めまいがする
上記症状が続く場合は、医療機関を受診して専門家に相談することが大切です。
五月病になりやすい人の特徴
- • 義務感や正義感が強く、手を抜けない
- • 完璧主義で、ミスや失敗を許せない
- • 仕事熱心で、プライベートを犠牲にすることに抵抗がない
- • 周囲を気遣うあまり、自分を雑に扱う
上記に当てはまる場合は自分を追い込みやすい方の特徴ですが、基本的にはどんな方でも発症する可能性はあります。
五月病の予防と対策
1. 自分のストレスを把握する
ストレスに対して対策を取るためには、どのようなストレスを抱えているのか、自分自身で把握する必要があります。
- • 不満や不安を紙に書き出す
- • 信頼できる人に話を聞いてもらうなどの方法を用いながら、理想と現実のギャップがどこにあるのかを見つけましょう。ストレスについて考える際は、オンオフを付けることも大切です。
- • 考える時間をあらかじめ決めておく(例:朝に考えて、夜は休む時間にする、お風呂の時だけ考える)
- • 考え事をするときの方法を決める(例:紙とペンがあるときだけ考える)
など、無理しないためのルールを作っておくことをおすすめします。
2. 悩みを言葉にする
ストレスの原因を見つけたら、それを信頼できる人に話してみてください。頭の中で考え続けるより、思考を言葉にするほうが、隠れていた部分が明確になりやすいです。周囲に相談できる人がいなければ、カウンセラーや臨床心理士など、専門家を頼るのもいいでしょう。客観的な視点が加わることで、新しい解決策が見えてくるかもしれません。
3. 自分ができることを探す
環境を変えるのは、そう簡単ではありません。環境のコントロールを試みるより、自分にできることを探すほうが取り組みやすいでしょう。
- • 苦手な人と気持ちよく付き合うために、まずは挨拶から始めてみる
- • 自分の思考パターンを考えて、思い込みや決めつけがないか探してみる
- • 新しい目標を決めて、それに向けて努力する
- • 家族や友達付き合い、自分の趣味など、仕事以外にも目を向ける
- • ひとりで考えることが難しければ、相談いただくのも方法かと思います
4. ストレスの原因を対処する
ストレスの対処法は、ストレスに「耐える」、ストレスを「そらす」、ストレスを「発散する」の3つです。
すぐに意識できるのは、ストレスを「発散する」方法です。
ストレスを発散する方法は人によってさまざまですが、大きくは2つに分けられます。
「即効性タイプ」は、仕事や学校に行きつつ、隙間の時間で取り組めることです。
- • 好きなものを食べる
- • 思い切り叫ぶ、歌う
- • クッションなどを思い切り叩く
- • 好きなテレビや音楽を楽しむ
- • アロマや入浴剤を使う
- • 呼吸を整える
- • 瞑想する
など、空いている時間にサッとできるストレス発散の方法を、いくつか自分の中にストックしておくといいでしょう。
「効果優先タイプ」は、土日や長期休暇など、時間があるときに取り組めることです。
- • 休日にスポーツを楽しむ
- • 近所の公園を散歩する
- • 旅行やドライブに行く
- • 趣味の時間を確保する
中でも、適度な運動は心身の安定につながります。 本格的なスポーツでなくても、「家の近所を散歩する」「意識的に階段を使う」「最寄駅の一駅前で降りて徒歩で帰宅する」など、体を動かす習慣をぜひ取り入れてみてください。



